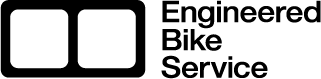オリジナルのクランカーバーを使用して、オールドMTBスタイルで街乗りからツーリングまで実現するVOKKAのお話。
今回は完結編。
VOKKAってなんじゃろ?とかのこのバイクのノリがわかる第一弾はこちら。

このVOKKAそのものを紹介している第二弾はこちら。

んでもって、この記事では第三弾、組み付けているパーツ紹介の後編を紹介させていただきますね。
今週のご紹介は…
Engineered Bike Service(EBS)VOKKA

この記事ではサイドから、そしてリアからご紹介。
イギリスのスポーツカーを彷彿とさせる高級感のあるブリティッシュグリーンをメタリックでペイントしているんですが、本来オーセンティックなロードバイクやランドナーなどに合わせられることが多いカラー。
それをアメリカンなスタイリングにしっかり落とし込んでいるんですが、ベストマッチすぎて驚きます。
組む前から可能性しか感じなかったけど、ここまで重厚感出せるカラーはやっぱりグッときますね。
カラーで魅せる高級感と質実剛健パーツの機能美が合わさる”大人感”。


基本的にはこのフレームカラーを活かすよう、ロゴやデカールのあるコマーシャルなデザインのパーツを極力使用せずにシンプルに、ミニマルな構成で乗っていただけるように注力。
服装に関わらずばっちり似合うバイクになっていると思います。
ラック取り付け時には一気に積載系バイクになるように。
前後NITTOで揃えているのですが、前後の高さが合ってる感じがたまらない。
フレームカラーは実は2色塗り分け。

ベースのカラーはブリティッシュグリーンをメタリック表現したジャガーグリーン。
唯一主張させてもらったEBSデカールのベースにはちょっとだけ無骨な隠し味。
Parkerizing Clear RAWを塗り分けで入れる。

RAWフィニッシュにしたい。
でもカラーも入れたい、というどっちも取るカラー。
いろんなところに塗り分けもできるので、メッキ仕上げと双璧を為す仕上げになりそう。
サドル周りはクラシックと実用の融合。
BROOKS B17 Specialレザーサドルで乗り心地と質感UP。

クロモリフレームと抜群の相性を発揮する革サドル。
使うほどに馴染むクロモリと同じ時を過ごして慣らして育てていく革サドルは乗り心地も自分に合ってきますし、しっかりと育てれば長く使えるのでコストパフォーマンスも良いです。
コスパとか、乗り心地、とかはもちろん伝えるべきことなんですが、革サドルと共に過ごした、いろんなところに行った年間単位での思い出ががなによりのメリットです。
内装式ドロッパーポストをチョイス。


ドロッパーってガッチリのマウンテンバイクとか、グラベルバイクだけのもの、って感じや空気があるけど、そんなことないです。
街乗りベースで使ったっていいし、もちろんツーリングにも。
重量としてのデメリットはありますが、それ以上に「常にポジションが出ている」ということの気持ちよさがあります。
乗って、降りて調整を繰り返すのももちろん良いけど、履く靴が変われば、その日のコンディションによって、ポジションってガンガン変わってくる。
同じビンディングシューズで走るバイクよりも調整の有用性があると思うし、もちろんグラベルライドでもバッチリです。
クランクセットはWhite IndustriesのMR30クランク+Camoシステム。

ホワイトのクランクはやはり永遠。
最近は削り出し系のガレージブランドがどんどん出てきたけど、やはりこのレベルで規格化されているクランクはないですね。
個人的にホワイトのクランクの記事は何本か書いていますが、書くたびに改めて良さに気付かされる最強クランク。
Wolf ToothのCamoチェーンリング採用。

CamoシステムはホワイトのクランクのPCD規格を変更するアイテムで、楕円のチェーンリングなどが発売されていて結構面白いです。
ニッチだし、レアパーツなのでいつか価値が出るのかな。
価値があるから、といって導入するわけではないですが、やっぱこういう変化球系アイテムは楽しいですね。

クランクアームとスピンドルはマウンテンバイク用を使用しています。
VOKKAはセッティングがわかりやすいです。
もちろんBBもWhite Industries。
ペダルはMKS XC-3。

VOKKAの迫力や体格、ボリュームに合わせるにはやっぱりそれなりに大きいペダルが欲しい。
EBS KYOTOでは基本MKSの日本製ペダルを採用していて、MKSは大きなペダルのラインナップが結構あるので選ぶのが楽しいと思います。
その中でも一際レトロなXCをチョイス。
昔のペダルの復刻版なんですが、再現度もすごいし、当然今の作りなので精度も、食いつきも抜群です。
前後ラックで迫力抜群。実用性もバッチリな街乗りマウンテンバイクスタイル。

何度も言いたい、この前後ラックの高さが合っている気持ちよさ。
別々のメーカーではなかなかこれは実現できませんね。
フロントと同じような装備が可能なラックになっていて、天板にバスケットOK、載せるのもOK、パニアバッグも取り付けOKです。
街乗りでグロッサリーパニア、ツーリングでガッチリパニアバッグで抜け目なし。
GROWTAC EQUALブレーキで機械式最強を手にいれる。

このブレーキが登場してからというもの、機械式ブレーキの勢力図が変わるだけでなく、油圧式ブレーキの分野まで侵食するほどに人気と評価を得ている現段階では対価格、対スペック共に超超高水準なディスクブレーキ。

このブレーキの最大の魅力は「調整がしやすい」ということ。
メカニック目線でももちろん大助かりな機能ですが、それ以上にやはりユーザーフレンドリーであることがこのブレーキを推す第一の理由です。
調整がどれだけしやすいか、とかは多分誰かが書いてくれてるかもしんない。
僕も詳細撮ってどこかでUPしますね。
リーズナブルに超ワイドギアをゲットする。

RDやカセットにお金をかけていくと、よりスムーズな変速、そして軽さが手に入ります。
でも、僕はあまりそこを重視していなくて(もちろん使いますが)、どちらかといえばここはどんどんアップデートされていく部分なので、新型が出た時にショックを受けない範囲でアップデートしていきます。

少し前でもこの51Tなんて上位グレードでしか存在しませんでしたが今は安価に(といっても大きいのでそれなりに価格は、、です)手に入り、なかなか便利です。
僕は貧脚も貧脚なので、軽いギアはほんと助かります。
特に、トレイルライドが大前提となっていないATBやフルリジッドMTBなどはエリアを限定せずに散策をすることが多いので、突発的な坂道やなぜか出会ってしまう急坂などに対応できる奥の手的ギアはとても大切です。
このDeoreは11速ですが、8速で組むのとそこまで値段が変わらず、この変化でこの価格なら、とおすすめもできますし、その価格差を許せる範囲だと思っているのでちょっと山の可能性や「やろうと思えばできる」性能を持たせたいオーナー様にはお勧めしています。
White Industries XMRハブでスーパーなめらか回転。

上質に回るハブ、といえばやはりこちらもホワイト。
軽くて、整備性が良くて、となればまずはこのハブをおすすめしています。
最近は値上がりが激しくて、いろんなハブを試していますが、少しずつおすすめできるハブも変わってきています。













今年はあと一本記事を書ければ、というところですが、年末年始はEBS KYOTOとしてはおやすみです。
お問い合わせは順番にご返信となりますので、ざっくりのご質問でも先に投げてきておいていただけるとスムーズかと思います!